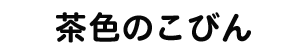03.ぼくとこびん
その話をおばあちゃんに話すと、おばあちゃんはニコニコ笑っているばかりだった。 冗談か、夢の話とでも思っているのだろうか。 でも、僕は至って冷静で、それでいて真剣なんだ。
「おばあちゃん……あの小びん生きてるの、ひょっとして?」
すると、おばあちゃんは、さらりと答えるじゃないか。
「もちろん、生きているよ。 だから、大事におしよ」
「茶色の小びんは、かたやきパンが好きなの?」
「おや、なぜだい?」
「かたやきパンをつまみ食いしたって、言い争いしてたよ」
おばあちゃんは、それを聞いて大笑いして丸い背中でのけぞった。 しわしわの口が大きく開いて、やせた歯を見せて笑っていた。 お母さんは、突然何事かと首をかしげながら、昼食の芋を焼いていたけれど、僕はますます混乱する。
「そうかい、そうかい、ビンさんが、かたやきパンをね。 それはゆかいだね」
「次からは、差し入れをした方がいい?」
僕は冗談のつもりで言ったのだけれど、おばあちゃんは大賛成した。
ひょっとして僕は、逆にからかわれたのだろうか?
僕はますます小びんを注意して観察するようになった。
仕事の合間に、手伝いの合間、僕は常に一瞬であっても必ず3回は小びんを見るようになった。 気が付くと、視線が小びんに向いているんだ。
「何をぼさっとしてるんだい、この子は!」
お母さんにパチンとこづかれて、僕はまたまた作業中だった手元に集中した。 でも、しばらくもしないうちに、また小びんの事を考え始めしまって作業にならないくらいだ。
一体、あの小びんは何なのだろう。
おばちゃんは相変わらず、マイペースにのんびりと、日向ぼっこがてらに揺り椅子を揺らしている。 視線の先をたどると、おばあちゃんの菜園が広がっていた。
それで、僕はこの時初めておかしいという事に気が付いた。 僕の知る限り、おばあちゃんはいつでも椅子の上の人であり、たまに立ち歩いても、菜園を手入れするような体力はない。
「じゃ、誰が菜園を手入れしているんだろう。 僕もお父さんもお母さんもめったに手伝えないのになあ? 」
今までどうして気付かなかったのか、それがむしろ不思議なくらいだった。
「あ、もしかして茶色の小びんがマメに手入れしてたりして!」
僕は笑いながら言ってみた。
すると、コトンッ――。
茶色の小びんが、タイミングよく、独りでに、何気なく、転がった。 そのまま沈黙を守ってはいたけれど、明らかに不自然だった、何もかもが。
「まさか、なあ。 あ、はは」
僕はにわかに、茶色の小びんがせっせと菜園を手入れしている姿を想像してしまった。 どうしよう、何だか冗談にならないぞ……。