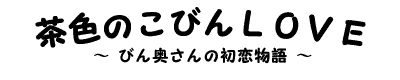03.ひぐらし旦那
『今日ね、変わった人を見たけたの』
その日の夕飯を家族みんなで囲んでいた時、びん奥さんはその若者の事を話した。 家族は始めの方だけ聞いて、あとは「ああ、何だ」と言わんばかりだった。 びん奥さんにとっては、思いもかけない反応だ。
『え、何、みんな知ってるの?』
『ああ、それきっと「ひぐらし旦那」だね』
『誰、それ?』
『その日暮らしでフラフラしている若者だよ。 村のはずれの小川辺りに住んでる独り者で、あれ、知らなかったのかい?』
ふるふると左右に首を振るびん奥さんを見て、家族もまた驚いたように訪ね返す。
『知らない。 その人いったい何してるの?』
『何してるかなんて、誰も知らないよ』
その話は、あっけなくそこで終わってしまったが、その時から、びん奥さんの中に「ひぐらし旦那」は確実に存在していた。 食後にお皿を洗って朝食用の下準備を整えて置いた時、ふと、びん奥さんの足に何かがコツリと当たった。 見ると小石である。 思わず拾い上げてみたが、どこから見ても造作も無い小石だ。
『別に、ただの石ころ、だよね?』
妙に昼間の印象が強かったのか、そのまま窓の外に放り投げるには忍びなく、そっと勝手口から転がした。 数回転がって、ぴたりと止まった小石をしばらく眺めてみたが、そんな自分がバカらしくなって立ち上がると、ぱたぱたとスカートを叩いた。
『何してるんだい?』
『別に』
びん奥さんは答えながら勝手口を閉め、何事もなかったように台所を後にした。
「それで? お母さんどうしたの?」
尋ねるびん娘は、身を乗り出しすぎて、坊ちゃんの頭から転げ落ちてしまった。
「大丈夫? 気を付けないと、大怪我するよ」
坊ちゃんが両手の平を広げて、目の前を落ちたびん娘を受けたから、とりあえず大怪我は免れた。 坊ちゃんの掌の上で、クルクルと目を回しているびん娘を、おばあちゃんは心配そうに覗き込む。
「あー、びっくりした! 死んだかと思った!」
「おやおや、元気だね」
「ねえ、それより、おばあちゃん続き! プリーズ!」
「はいはい」
「やっと見つけた!」
しかし、そうは問屋が卸さなかった。 大きな声がした方を振り返ると、びん奥さんが小さな仁王に構えて立っていた。 坊ちゃんの掌に載っているびん娘を降ろしてもらうように伝えると、そのままむんずと耳を捕まえて引っ張り降ろす。 びん娘が暴れながら叫ぶ。
「痛い、痛いってば! おばあちゃんの話聞きたいんだってば、放してよ、お母ぁさん!」
「ダメ! まったく目を放すとすぐこれだ。 忙しいんだから手伝いくらいしたらどうだい、ここに入り浸って!」
そのまま、びん奥さんは坊ちゃんとおばあちゃんに丁寧に挨拶しながら、びん娘を引っ張っていった。 そこら辺まで、びん娘の声が聞こえていたが、それもすぐに聞こえなくなった。
「あらあら……どうしようねぇ、話の続き」
「続けてよ、おばあちゃん。 僕が聞くよ」
「びん娘はどうしようねぇ?」
小さな二人が出て行った方を眺めながら、おばあちゃんが目を細める。 坊ちゃんは片手を顎にあてて、しばらく考え込んだあと、いたずらっ子みたいな笑顔を見せた。
「そうだな、いいんじゃない? びん娘には内緒にしておこうよ、もう少し。 秘密、秘密」
坊ちゃんが出した提案に、おばあちゃんは束の間考えて、そして坊ちゃんに同意した。 そのシワシワの目元には、どこか茶目っ気が見え隠れしていた。
「じゃ、続けるよ」
びん奥さんは、ひぐらし旦那の事を聞いてからも、いつもの通りに日常を送っていた。 家事をこなしながら、言い寄ってくる若い衆は、ことごとく振り払い、たまには友達と遊びに出かけた。 それに、ひぐらし旦那の方も、それきり長い事姿を見かけなかった。
「え、そうなの?」
「そうなんだよ。 実際、おばあちゃんも見かけなかったね」
「うちの近所に、そんなにいるの? 『びんに住む小人族』って……」
「良く見ていればね。 同じように生活しているんだよ、小さいだけなんだからね」
「僕ちっとも気付かなかったよ」
「普通はそんなもんさ。 気付く方が稀なんだよ」
一方で、びん娘は空になった洗濯籠をひっくり返して座り込むと、母親を見上げてぶーたれた。
「せっかく、おばあちゃんの話聞いてたのに!」
「人のいない所で、勝手に盛り上がってるんじゃないよ。 それもこれも、全部あの人のせいだ、旅に出てばっかりで家に少しも居座ろうとしないんだから! 初恋は良かったね、まったく!」
「あーあ、またその話かぁ」
「ほら、他にもする事が山ほどあるんだから、いつまで座ってる気だい」
「もぉー、お母さん!」
いい天気だった。 空はどこもまでも青く、風は暖かく心地よい香りを伴って吹いてくる。 一年前もこんな天気の日だった。
「そっか、こんな日だったな。 元気かな、お父さん」